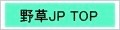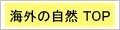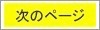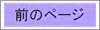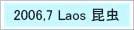アリ/ツムギアリの巣
2007年夏のラオス パクセー郊外にある名前が出てこないが大きな滝のある観光地に立ち寄ったとき、駐車場から滝を見る展望台に向う途中で撮影したもの。この時霧が出ていて滝を見ることができなかったが、この滝から立ち上る水しぶきや霧によって湿潤な森ができ、ランやシダの宝庫になっているとかで、観光客目当てのランやシダの売店がいくつも出ていた。それらに目がない当方はちっとだけわがままを言って同行の学生さん達と離れて一つの屋台を覗かせてもらったが日本のラン展では見たことのない野性のランをいくつも見つけた。日本に持ち帰ることはできないので値段だけ通訳に聞いてもらったところ、日本の1/60、つまり日本のラン展などで購入すると1株3000〜5000円のものが50円程度。絶対ここにはまた来てランやシダの撮影三昧の生活をするぞと夢想した。
ここに撮影したアリの巣は、この地域ではたくさん見られる着生シダの展開葉を折り畳んで巣にしたもの。3mmほどの小さなアリがビッシリ集まっていた。
2007.08.10 ラオス パクセー郊外
2007.08.10 ラオス パクセー郊外


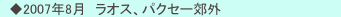
アリの巣_2007 / 2007.08 パクセー郊外
( Youtube動画再生 00’15)

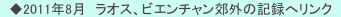
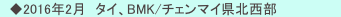
ツムギアリの巣の採取01_1602BMK
( Youtube動画再生 03’27)
ツムギアリの巣02_1602BMK
( Youtube動画再生 00’57)
ツムギアリの幼虫調理01_1602BMK
( Youtube動画再生 03’31)








それぞれの動画の説明は各Youtube説明文を参照下さい。


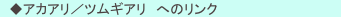
2015.08 HHL/ 2007 Laosにリンク
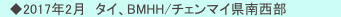
ツムギアリの巣の採取道具01_G1702BMHH
( Youtube動画再生 03’11)
ツムギアリの巣の採取03_G1702BMHH
( Youtube動画再生 03’15)
youtube動画に附した説明
「ツムギアリの巣の採取道具01_G1702BMHH」
GONGOVA 2017,国際協力研修,環境,村人の生活,ツムギアリ,ツムギアリの巣,巣の採集道具,自然環境から培われた伝統的な技術・知識を見る
冒頭は、長い竹竿の先にビニール袋を付けた道具?を担ぐ村の婦人を見かけた。育磨氏が何をしに、どこに行くのか尋ねたところ、遠くという回答。村人の遠くと云う表現は日本の距離感覚より遥かに遠いので、残念だったが付いて行くのを諦めた。それから数日経った夕方、幼稚園前の広場の1本の木に研修の賄いをしてくれている村の若いご婦人たちが竹竿の先にバケツを括り付けて何かを採集しているのを見て、すぐにピンと来た。それが採集シーンの映像。
後半は、チェンマイ市内の大きな朝市で、村と同様な手段で採集したと思われるツムギアリの卵やサナギが売られているのを見つけた。
「ツムギアリの巣の採取03_G1702BMHH」
GONGOVA 2017,国際協力研修,環境,村人の生活,ツムギアリ,ツムギアリの巣,
自然環境から培われた伝統的な技術・知識を見る
2016年2月に取材したBMKでは道具を使わずにツムギアリの巣を採集していた。ここでは竹竿の先に採取した巣を受ける容器をセットし、竹竿の先で巣を突き崩し巣の中の卵やサナギを振り落としたところを容器で回収するという、BMKより少し高度な採集方法が見られた。
GONGOVA=Grassroots Overseas NGO Volunteer Activity Programme
GONGOVA HP http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~19731706/index.html
GONGOVA 2017,BMHH / タイ国、チェンマイ県南西部 白カレン族居住山村
BMHH=Ban Mai Huai Hia, Chom Thong, Chiang Mai, Thailand








上掲4点の写真はMr.Y.Yamada氏のデータからトリミングしたものです