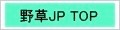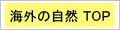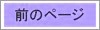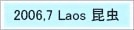アリ塚/シロアリの巣
2006年夏のラオス ナンヤン村の綿畑で撮影したもの。綿畑と言っただけではその大きさが想像できないと思うが、およそドーム球場のグラウンドと同じかそれよりやや広いかも知れない赤土の多少起伏のある土地に、まだ背の低い綿が一面に植えられている開放的なところである。その所々に赤土が大きいものでは人の背丈ほど盛り上がっていて、それらはみなシロアリの巣であるという。 興味津々の当方の顔色を見て村の人が近くにあった巣を壊して中を見せてくた。 白い帽子は村の人、オレンジの帽子は情報局のスカサワン氏。
ほんのわずか表面の土を削るとそこにはすぐにシロアリの住処となる通路や居住区となる複雑な形の穴や空間が現れる。表面は多少の大雨でも雨漏りや土が流れてしまわないように堅く滑らかに成らされている。内部は更に堅く乾いていた。これを2〜3mmほどのシロアリが作ったのであるが、どのような工程でここまで大きくしたのか興味が尽きない。
もう一つの興味は、村人はなぜこの蟻塚を作物の畑に放置するのか、蟻塚を許容しているのかということである。
先にこの綿畑のカメムシのところで書いたが、村人は害虫であるカメムシやバッタを放置しているというか許容している。
このような疑問に気がつくと同時に、何故その場で村人に尋ねなかったのか、その取材力のなさに我ながらがっかりする。
カメラを回していると、撮影しているという行為・作業に没頭し、そこである種作業として完結してしまっているというのもあるが、取材者としてはまだまだ未熟であるという証しでもある。いつでも再訪できるところではなく、非常な幸運に恵まれて取材・撮影の機会を得ていることをもっと真剣に受け止めなければならないと反省する。
2006.08.05 ラオス ナンヤン村
2006.08.05 ラオス ナンヤン村


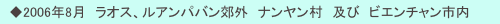
シロアリ1_2006 / 2006.08 ナンヤン村(ルアンパバン)
( Youtube動画再生 00’31)
シロアリ2_2006 / 2006.08 ナンヤン村(ルアンパバン)
( Youtube動画再生 00’24)
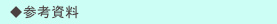
2012年10月タイ HHL/チェンライ 白カレン族の村のナマズ養殖池でシロアリの巣を削って中にいたシロアリをナマズの餌にしているのを撮影し、シロアリの巣を放置する理由の一端を垣間見た。またHHLではシロアリの巣(蟻塚)の上に木の枝や葉を置きシロアリの餌にするなど、シロアリの飼養に積極的な習慣も見られた(2013年3月)