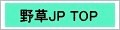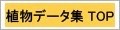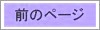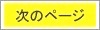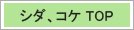1998.04.07 自宅
ウラボシ科 ノキシノブ属

タイワンラシャシダ/Lepisorus thunbergianus
2008.03記:入手してからずーっと手製のヘゴ鉢で育ててきたが、一昨年(2006年)頃からコンディションが悪くなってきたので、この冬、ヘゴ鉢ごと2つに割って、現在は養生のため素焼き鉢にヘゴ鉢ごと水苔で包んで入れている。既に新しい芽が伸びてきているのである程度根茎が新しいものに更新したら、またヘゴ鉢を作って植え替える予定。
2008.03.08 自宅




2009.03.20 自宅
2009.04.04 自宅
右上(2008年)の鉢が1年経った状態。水やりさえ怠らなければ、かなり丈夫なシダなので当方のような無精な者の手許でも次々に新しい葉を展開してくれる。ヘゴ鉢に移植するのはもう少し大きく安定してから。


2010.09.25 自宅
2010.09.25 自宅
2010.10.02記:そしてまた1年半経過した状態。左の平らな薬草を干す竹の網の直径は60cmあるがそれを越している。右は同じものを角度を変えて撮影したもの。
素人園芸の醍醐味は育つに任せて大株にすることであるが、悩みはあまり大きくすると置き場に困ることと、できるだけ全体に陽を当ててあげようとしても移動が大変だし、同じところで鉢を回転させるのが関の山。
ここまで大きくなったら安心してヘゴに移せるのだが、大きなヘゴだと冬の置き場困るしやはり株分けかな。と考えないではないが、これ以上鉢の数も増やせないし----。これはシダ趣味の人からみたらすごく贅沢な悩み。自己満足の世界。枯れなければそれに超したことはない。

2012.02.24 自宅 2009年に小分けした鉢の株も大きくなって来た

2012.06.01 自宅 左の鉢の6月の状態。葉の数が増えている。



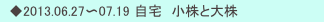


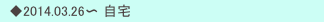

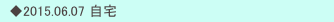




2013年の記録にある小さい方の株は人に譲ってしまったため現在はこの一鉢のみ。といいながら大きくなりすぎたので、また株分けをしなければ根詰まりで窒息してしまいかねない。
株分けするのはいいが、鉢が増えると冬場の置き場所に困ってしまう。ほかのシダも大きくなってくれたはいいが------。
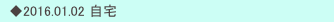


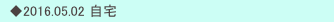
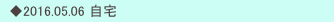

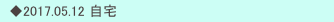

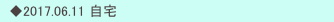


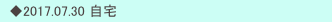

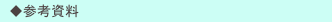
ラオス、タイ(チェンライ、チェンマイ)のイワダレヒトツバ?
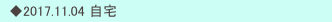

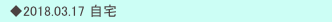


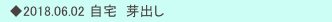

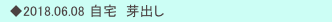

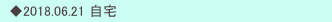

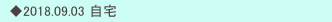

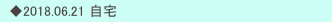


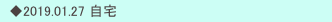




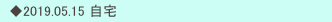

◆2020以降の記録は上の写真または次ページから

※2020.12.14記:これまでイワダレヒトツバ/ウラボシ科 ヒトツバ属として誤記していたのを修正