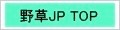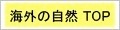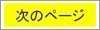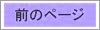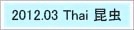テントウムシ/Coccinellidae
村に向かう日の朝、ホテルの脇にある空き地で撮影した。大きさは日本のヒメカメノコテントウ程。はじめ、マメ科の花の中に潜んでいるのを見つけ、それからは草むらのあちこちで見つけた。胸、頭の模様は同じだが、翅の模様が異なるものを数タイプ見つけ撮影した。模様からすると、沖縄で撮影したダンダラテントウに似ている。リンクは張っていないが、やはり沖縄で撮影したハイイロテントウは大きさも模様も良く似ている。ハイイロテントウはアメリカから米軍の貨物と一緒に運び込まれたという解説を読んだことがあり、当方の資料を見返すとサンフランシスコの記録に残っていたのでリンクを張ることにした。
本来文頭に記すことかも知れないが、タイ、ラオスでテントウムシを見たのはこれがはじめてだったような気がする。
2012.03.27 チェンライ市内のホテル脇/マメ科の野草
2012.03.27 チェンライ市内のホテル脇の空き地/イネ科の野草についたアブラムシを捕食しているところ
2000.08 サンフランシスコで撮影したテントウムシ
2011.02 沖縄で撮影したダンダラテントウ


2012.03.27 チェンライ市内のホテル脇の空き地



2012.10.11 チェンライ市内のホテル脇の空き地 3月と同じ空き地でテントウムシを探し撮影できた。関心の一つは3月と10月で個体の大きさに違いがあるのか。ここで見られるテントウムシは日本のものよりかなり小さい。季節によって差があるかを見たかったが、差はない。小さい。
ただ上の2点に示すようにダンダラ模様ではないタイプも見つけた。下は3月同様ダンダラ模様のタイプ。
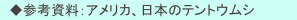
コウチュウ目 テントウムシ科
テントウムシ01 1203Thai / 2012.03 チェンライ市内
( Youtube動画再生 00’44)
テントウムシ02 1203Thai / 2012.03 チェンライ市内
( Youtube動画再生 00’20)
テントウムシ03 1203Thai / 2012.03 チェンライ市内
( Youtube動画再生 00’49)
テントウムシ04 1203Thai / 2012.03 チェンライ市内
( Youtube動画再生 00’42)
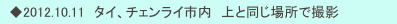





2012.09 アラバマで撮影したテントウムシ
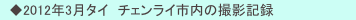
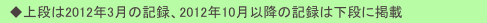
テントウムシ1_1308Thai/2013.08 HHL
( Youtube動画再生 00’35)
テントウムシ2_1308Thai/2013.08 HHL
( Youtube動画再生 02’06)
テントウムシ3_1308Thai/2013.08 HHL
( Youtube動画再生 00’31)
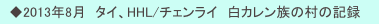
※ジャンプしてきた元のページに戻る時にはブラウザーの戻るボタン「◀」で戻ってください。








2013年8月 HHL いずれも水田地域で撮影したもの。これまでチェンライ市内での撮影記録はあったがHHL村内では今回が初めての記録。HHLで特に珍しいというのではなく、あくまで当方との巡り合わせの問題。自然農法の村にとってはテントウムシはアブラムシなどイネの害虫を食べる益虫。雨季の水田地域に入ったのが初めてだったのでテントウムシとの出会いも初めてとなったのかも知れない。
オオテントウ01_1408Chi/チェンライ市内
( Youtube動画再生 02’24)
オオテントウ02_1408Chi/チェンライ市内
( Youtube動画再生 00’39)
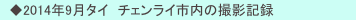



2014.09 帰国の前日、チェンライ市内の自然の撮影時、コック川の橋の下で見つけた。上に挙げているように、チェンライ市内で何度もテントウムシを撮影してきたが、それらは日本のテントウムシの半分もないくらいの小さな個体ばかりであった。今回撮影したものは映像から伝わるか疑問であるが、日本で見られる種でいえばカメノコテントウくらいの大きなタイプの個体であった。カメノコテントウとの共通項はドイツ軍のヘルメットのように甲殻の縁が外に開いているところ。これまで市内で観察した小さなタイプはどちらかというと星紋よりダンダラ系の模様が多かったが、これは見てわかるように明瞭な星紋。ラッキーな出会いだった。
※後の調べでこれは「オオテントウ」らしいことが見えてきた。東南アジアに多く分布するということが大きな拠り所。 オオテントウは日本3大テントウムシの1種で、既にカメノコテントウ、ハラグロオオテントウを記録しているので、「オオテントウ」を加えることができれば3種を揃えたことになる。子どものカード収集みたいなもの。小さな、細やかなマイルストンを踏み越える喜びはある。貪欲な分析眼で正確さを失っているかも知れない。