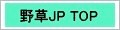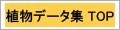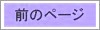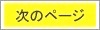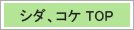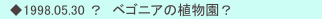
ツルシダ科 タマシダ属

タマシダ/Nephrolepis cordifolia
タマシダは観葉植物としてツデーという名前で出回っているので、アジアンタムという名前で流通しているハコネシダやホングウシダの仲間と同じ身近な存在のシダの一つ。ヒトツバのところで1990年頃八丈島に行ったとき、ヤシに着いたヒトツバを剥がしたのをもらってきたことを書いたが、下の写真は幕張で撮影したもの。
八丈島に行くまえに三宅島にも行っている。1983年の前の噴火からしばらく経っていたが、溶岩が海に向って流れた後が、黒く生々しく残っていた。そのまだエッジが鋭い黒いガラスのような溶岩のガレ場に幼いタマシダが根を張ろうとしていた。何年かしたら、そこはタマシダの緑で覆われているだろうと推測した。2000年の噴火のとき真っ先に思ったのは、タマシダやシュスラン、ナギランといった植物のこと、アカコッコという鳥のことだった。
火山の噴火ということでは1995年頃にハワイ島に衛星通信を利用した遠隔教育の実験を取材に行った時、カナダの若い女性科学者とキラウエア火山の溶岩が海に注ぎ落ちる少し手前のところを歩いた。一緒に取材に行った仲間から40〜50m程先行する形となって溶岩の流れが見えるというところに向っていたところ、後から来る仲間が「危ない!」と叫ぶ声が聞こえた。後ろを振り返ると、ほんの数メートル通り過ぎたところで、新鮮な?溶岩が固まりつつあった溶岩を持ち上げ、真っ赤な割れ目を作っていた。噴水のように噴き出すタイプの溶岩であったら、あの時点この世とはお別れしていた。それでどうなったのかというと、後戻りはできない、前に進むしかない。ところが、前にも行く手を阻むように後ろと同様に溶岩が地面を割り顔を覗かせはじめていた。科学者は少しの間その場に立ち止まり状況を見ていた。それまで他の研究者が辿った踏み跡を辿っていたのだが、意を決したようにそれまでとは異なる踏み跡のない溶岩の上を進み始めた。こちらはただ付いて行くだけ。周囲を見回すとほんの数メートル離れただけのところのあちこちで地面が割れて赤い線が出来たり水蒸気の白い煙を噴き始めていた。真に溶岩のただ中という感じ。こちらは科学者が安全な戻り道を探しながら進んでいるのかと思っていたのだが、しばらくして小高い丘のようなところを回り込んだところが溶岩採集の実験場になっていた。研究者魂と言うかなんというか、目的地に向って突き進む姿勢に脱帽。
実験場では夜行うことになる衛星中継の準備中だった。そこには1m位の丸い穴が開き、覗き込むと自分の立っている足下から1mもしないところを、真っ赤な溶岩が川の流れのようにかなりのスピードで流れていた。そこまで歩いてきた足下はすべてこの状態だったという。流れを阻むものがあると、それを避けて流れようとする力が働き、穴があったり地表の溶岩層の薄い部分があるとそこから流れ出すのだという。
しばらく撮影をした後また科学者と元の場所に戻ったのだが、その時は溶岩の滲み出しのような状況はなかったというか観察する余裕もなく先を急いだ。
後日、夜中に行われた衛星中継の映像を見た。当方が歩いたのは昼間。だから溶けた溶岩の発する色は見えていても「光」は見えていない。ところが夜の実験場の光景を見てびっくりした。地面を割って滲み出す溶岩はその周囲一帯を真っ赤に染めていた。赤く染まったところは相当な高温になっていることを示していた。とんでもないところを歩いたのだと後になって理解した。
それもいい思い出。また生きている地球の生の姿と触れ合いたい。
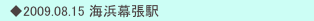







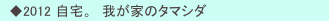

2012.06.01 自宅
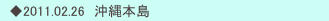
2012.02.24 自宅
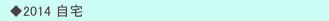


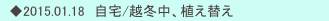



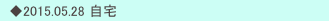
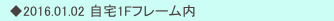

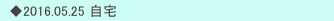

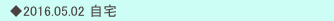

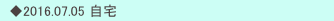

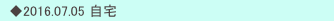

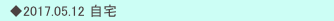


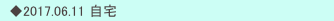


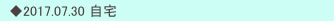


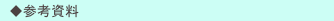
タイ(チェンライ , チェンマイ)のタマシダ
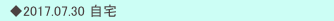


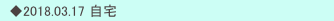


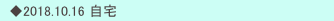


根鉢の脇にはみ出している根や脇芽を全て綺麗に刈り込んで2回り大きな鉢に赤玉+鹿沼混合土で植え替えた。玉状の茎はマキシラリア。元々はマキシラリアの鉢だったものがタマシダに占領された状態。でもマキシラリアを生かしていれば、春先にマキシラリアの黄色い花も楽しめる。タマシダもこれを含めて4鉢もあり、それぞれ株分けをしないと窮屈そう。これも譲り先を探すのが大変そう。どなたかまとめて引き取ってくれれば良いのだが。
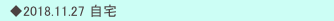


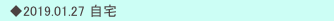


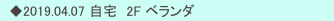




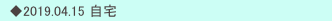


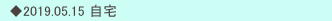


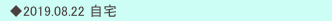


◆2020以降の記録は上の写真または次ページ