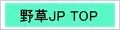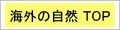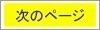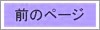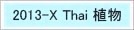ショウガ科?(リップ紅)
ショウガ科 属
2013.08 HHL 村の南の尾根を下って沢に近づいた辺りおよび沢筋にも数株見つけ撮影した。はじめに見つけたのは村の青年であり、彼はこの花を当方に見せるために登りと異なる道を選んだように思えた。というのは、この花は花は20mm程もあり大きいのだが草体そのものは高さ5〜6cmしかなく、他の野草やシダの葉に覆われていてなかなか人目につかない。彼は何か匂いでも嗅ぎ付けるのだろうか所々で立ち止まって草の葉をかき分け探していた。そして当方がこの花をひとわたり撮影した後はその草をかき分ける仕草は見せなくなったことから、この花に特に集中していたように思えたのだ。
2013年10月になってこの文章を書いているのだが、これがショウガ科のものか疑問が強まっている。茎や葉を見ると別に記した地生ランと良く似ているようにも思えてくる。いつものように疑問符付きのまま置いておくことにしよう。
参考資料に2013年10月我が家で撮影したミョウガ(ショウガ科)の花を載せておく。
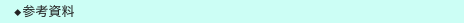
2013年10月13日我が家の茗荷(ミョウガ/ショウガ科)の花。今年は遅くまで芽(花)を出す。
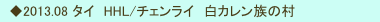




ショウガ科小花_1308HHL /2013.08 HHL
( Youtube動画再生 01’18)
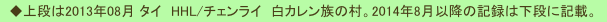
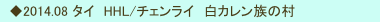
ショウガ科リップ紅a_1408HHL/南の沢
( Youtube動画再生 01’03)
ショウガ科リップ紅b_1408HHL/東の沢
( Youtube動画再生 01’05)
ショウガ科リップ紅c_1408HHL/東の沢
( Youtube動画再生 00’43)
ショウガ科リップ紅d_1408HHL/東の沢
( Youtube動画再生 01’36)
ショウガ科リップ紅え_1408HHL/東の沢
( Youtube動画再生 01’07)







2014.08 HHL/東の沢:この花を始めに観察したのが村の南の尾根に上がる途中の斜面であったため、東の沢や西の沢で見つけたときはうれしいというか、苦労して南の尾根に上ることはなかったのかとチョッと拍子抜けする気分も味わった。動画の1点目は南の尾根に上る途中のものだが、それ以外の4点は東の沢に下りて行く途中の明るい場所で、花が低いところで咲いているので、どうしても道路に寝そべらないと撮影できないのだが、その分カメラをしっかり保持できるので、南の尾根や沢で撮影したものよりピンが来ているようだ。
村人はこの花や新芽を食用にするということだ。
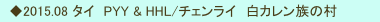
タイ・ショウガ科リップ紅07_1508PYY
( Youtube動画再生 01’47)
タイ・ショウガ科リップ紅08_1508HHL/東の沢
( Youtube動画再生 01’37)




2015.08 PYY:Youtube の説明の流用
パレーキ村の中心から水田方向にほんのわずか進んだところで見つけた。というか、村へ帰る時に見つけたので、水田方向に散策に向かった時には見落としていた。
パレーキは一つの種がまとまって生えている場所がある。このショウガ科の草も数種のショウガ科の種も数株見受けられるが、ほとんど単相といっていいほど単一な種で覆われている。
パレーキに人が住み始めたのは精々3、40年程前だという。新しい村作りのために川沿いの崖に道を造ったとき川側の縁が石や土がむき出しになったため、水に強いショウガ科の植物をほかから持ってきて植えたのではないか。それで選択されたのであれば、単に補強用だけではなく別な利用目的もあったのかと推測できる。あくまでも推測、自分の立てた仮説を確かめるのもこれからの楽しみ。2014.08の説明の最後に書いた「新芽や花を食べる」というのがこの感想の伏線。


2015.08 HHL 東の沢筋:
こちらは動画のサムネイルを見て分かる通り、パレーキと比べると林道の幅が広く、山側の傾斜も緩やか。ここもこのショウガ科の野草が群れを作っていた。この沢筋で時期を違えながら順に咲いて行くのかも分からないが、昨年、一昨年と撮影した場所が違い、偶然だろうが順に村から遠ざかっている。これも観察を続けないとわからない。
※ジャンプしてきた元のページに戻る時にはブラウザーの戻るボタン「◀」で戻ってください。